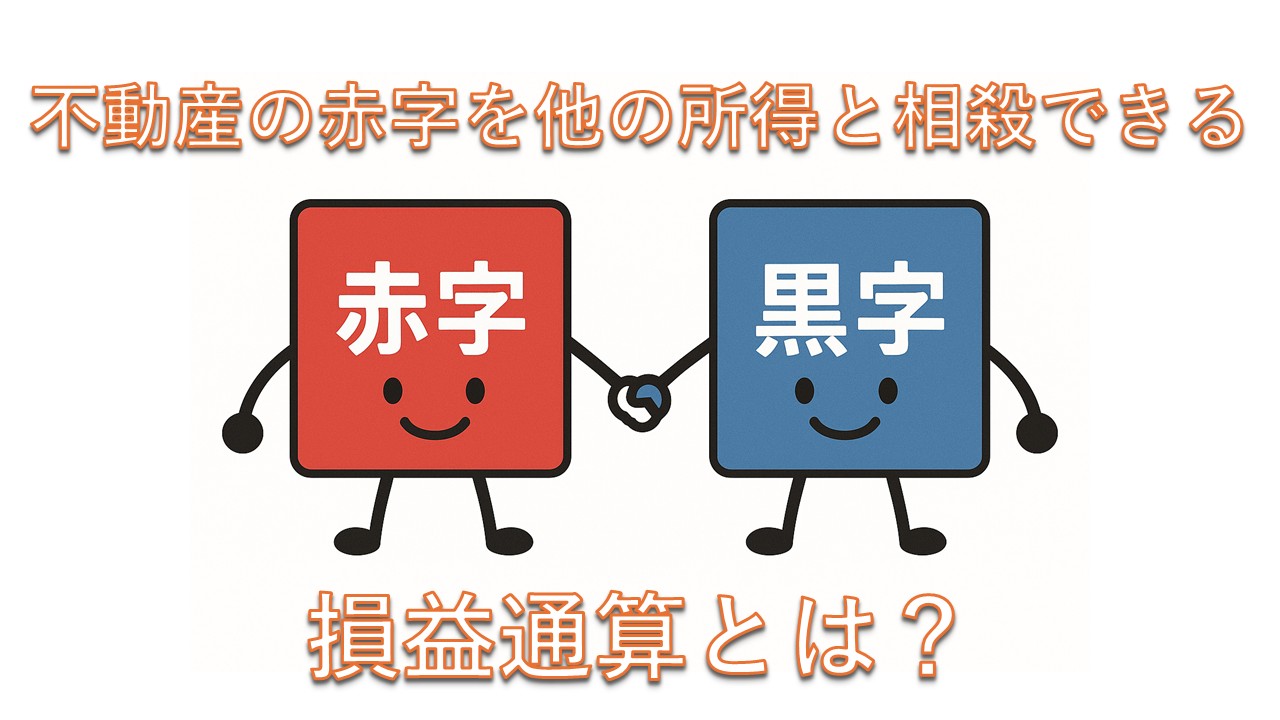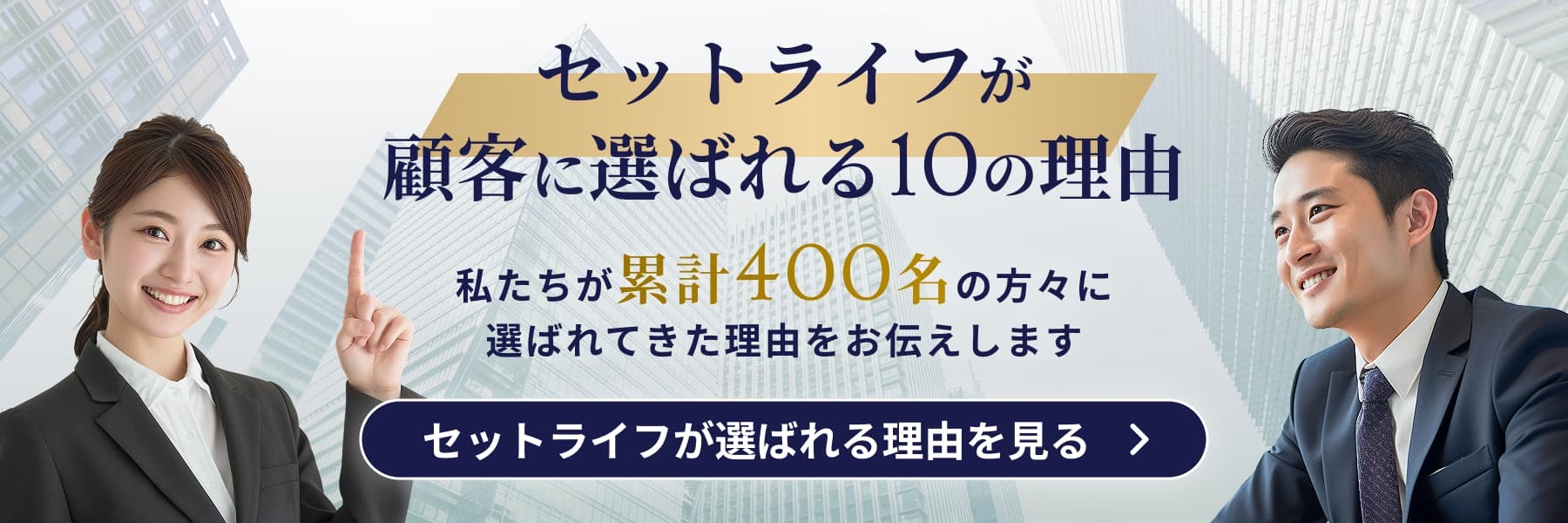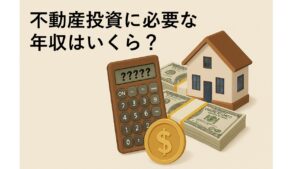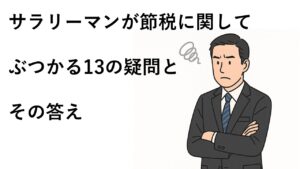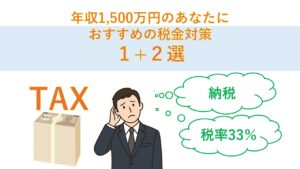不動産における損益通算とは?
損益通算とは赤字を他の所得と相殺できる制度
損益通算とは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得などの所得区分で赤字が発生した場合、その赤字を給与所得や事業所得など他の所得と相殺できる制度を指します。
例えば、会社員が給与所得を得ながら副業として不動産投資を行い、投資で赤字が出た場合、その赤字を給与所得から差し引くことで課税所得を減らせます。
※出典元:国税庁より
仕組み
課税所得 = すべての所得の合計 - 各種所得控除
この計算において、不動産で赤字が発生すると合計所得が圧縮されるため、結果的に所得税や住民税が減少します。
損益通算の具体例
- 年収:1,000万円(給与所得のみの場合、課税所得:約650万円)
- 所得税率:20%、住民税:10%
この場合の税負担は概算で以下の通りです:
- 所得税:約87万円
- 住民税:約65万円
- 合計税負担:約152円
ここで、不動産投資で年間100万円の赤字が発生した場合、課税所得は650万円 → 550万円に圧縮されます。
圧縮後の税負担
- 所得税:約67万円
- 住民税:約55万円
- 合計税負担:約122万円
節税効果:約30万円
実質的に、不動産投資の赤字によって税負担を減らすことが可能になります。
なぜ不動産投資家は赤字を作ってまで損益通算を狙うのか?
損益通算すれば節税になるから
損益通算の最大のメリットは、給与所得など本業の所得にかかる税金を減らせることです。税率が高い高所得者ほど、損益通算による節税効果は大きくなります。
不動産所得は経費次第で赤字になりやすい
不動産投資では主に以下のような経費を計上できます。
- 物件の減価償却費
- ローン金利
- 管理費・修繕費(一定条件あり)
- 固定資産税
特に、減価償却費は実際の支出を伴わない「帳簿上の経費」であるため、キャッシュフローが黒字でも税務申告上は赤字にできるケースがあります。
税務申告上の赤字は投資家にとって問題ではない
損益通算での赤字は「帳簿上の赤字」であり、実際に資金が減っているわけではありません。
例えば、
- 家賃収入:300万円
- 経費:200万円
- 減価償却費:150万円
この場合、帳簿上の所得=▲50万円(赤字)ですが、キャッシュフロー(実際の現金収支)は+100万円(黒字)となります。
資産が増え、キャッシュフローが回っている限り、会計上の赤字は投資家にとって問題にはなりません。
つまり、黒字でも赤字でもどちらでもメリットがあるので気にならないという事なのです。
節税目的で損益通算を狙うことの限界
税務署に損益通算が認められないことがある
過度に赤字が続くと、「事業実態がない」と判断されるリスクがあります。節税目的だけで購入したと疑われると否認される可能性もあるため注意が必要です。
つまり、不動産投資とはあくまでも資産形成の手段であり節税効果は副次的なものであるという事です。
建物がない土地だけの投資では損益通算できない
損益通算の対象となるのは不動産所得であり、建物のない土地(更地)では減価償却ができず赤字化は難しいです。
しかし、駐車場などでも何かの機械など設備を導入していた場合はその限りではありません。
特定の所得は損益通算の対象外となる
損益通算はすべての所得に適用できるわけではありません。所得税法では、各所得を「総合課税」と「分離課税」に分け、それぞれの課税方式ごとに通算可否が異なります。
特に利子所得・配当所得・株式譲渡益・FXなどの雑所得といった「申告分離課税」や「源泉分離課税」の対象は、不動産所得との損益通算ができない点が重要です。
※出典元:国税庁より
損益通算できる所得
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
- 譲渡所得
損益通算できない所得(分離課税・源泉分離課税)
- 利子所得(預貯金の利息、公社債の利子など)
- 配当所得(株式配当や投資信託の分配金のうち申告分離課税選択時)
- 株式譲渡所得(株式・投資信託の売却益)
- 先物取引やFXの雑所得(申告分離課税)
税法上、損益通算が認められないのは課税方式の整合性を保つためです。
- 株式やFXなどは「申告分離課税」で一律20%程度の税率が適用されます。
- 一方、給与や不動産所得は「総合課税」で累進税率が適用されます。
この2つを混ぜると、税率が異なる所得区分間での不公平が生じるため、通算は不可とされています。
「雑所得」は広範囲ですが、以下のように扱いが異なります。
- 事業的規模の副業 (事業所得)→ 損益通算対象
- FX・仮想通貨・先物取引の雑所得(申告分離課税) → 損益通算不可
副業の収入と投資関連収入では課税方式が異なるため、同じ「雑所得」という名前でも区分を確認する必要があります。
例えば、会社員が副業(事業的規模)で赤字を出した場合、不動産赤字と合わせて損益通算が可能です。
しかし、これを税務署が否認するケースもあり「事業性の有無」が争点になります。
不動産所得の損益通算が有効なのは総合課税対象の所得に限られるということになります。
- 給与所得+不動産赤字 → 節税可能
- 株式譲渡益やFX利益との通算 → 不可
- 雑所得は「副業が事業的規模(事業所得)か、そうじゃない(雑所得)か」を要確認
節税計画を立てる際は、対象所得の課税方式を必ず確認し、通算可能な所得とそうでない所得を区別することが不可欠です。
補足:過剰な損益通算は制限される可能性がある
過去には、海外不動産投資を利用した損益通算スキームが節税目的で乱用され、現在は海外不動産の損益通算は認められなくなりました。
最近はタワマン節税なども規制の対象となっています。
節税に関しては今後も制度が制限される可能性があるため、節税だけを目的とした投資はリスクが高いと言えます。
損益通算に惑わされない資産形成を目指そう
節税目的の投資が危険な理由
不動産投資を検討する際、損益通算による「節税効果」を前面に押し出す営業トークは多く見られます。しかし、節税を目的化した投資は以下のリスクを伴います。
-
物件選定が歪む
節税効果だけに着目すると、利回りや立地などの本質的な資産価値を軽視しがちになります。その結果、長期的に見た時に資産価値が下がる物件を掴むリスクが高まります。 -
ローン返済の負担増
節税のために過大なローンを組んでも返済は確実に発生します。節税による減税効果は一時的であり、ローン返済のキャッシュアウトが長期的に重くのしかかります。 -
減価償却終了後の税負担増
減価償却が終わると、帳簿上の赤字がなくなり節税効果は消失します。結果として税金負担が一気に増加し「想定外の税負担増」に苦しむ投資家も少なくありません。 -
税制改正リスク
海外不動産損益通算の廃止のように、節税スキームは将来的に規制される可能性があります。節税依存型の投資は、税制改正に直撃されやすい脆弱な戦略です。
節税効果の中核である減価償却で一番効果が高いのは地方などの場所にある築古アパートです。
しかし、これは一時的な節税効果を生むだけでトータルの出口戦略で言うとリスクが高く非常に難易度の高い物件選択になります。
不動産投資はあくまでも資産形成の選択肢の一つという事を念頭に置いて間違った選択をしないように注意しましょう。
資産形成型投資の基本指針
損益通算は「結果として節税につながる」副次的効果程度にとどめ、以下の資産形成軸を最優先に据えるべきです。
不動産による資産形成の基本
- 資産価値の維持
これは将来的に不動産を持ち続けるにしても売却するにしても重要な要因であると言えます。立地・需給・建物状態を重視し、長期的に資産価値が落ちにくい物件を選ぶことが重要です。特に駅近・人口増加エリア・再開発地域などは下落リスクが低く、将来的な売却益も期待できます。 - 購入時の自己資金
物件購入時におそらくほとんどの方が金融機関からの融資を受けて購入をするかと思いますが、その際の自己資金(頭金)は損益通算には含めませんので単純に手元の資金の支出になります。減価償却費は純粋な建物代から計算されますので、自己資金を出しても出さなくても金額としては変わりません。自己資金の条件が出ない満額評価をしてもらえる物件を選択した方がいいでしょう。 - 出口戦略
何の目的で不動産を所有するのか?この目的を最初にはっきりさせておかないと出口戦略において失敗をしてしまう可能性があります。なんのための資産形成なのか?これを元に最終的に不動産をどうするかを決めて出口戦略を事前に決めておきましょう。
「損益通算に頼らない」投資家の強み
資産形成型投資を行う投資家は、減価償却終了後や税制改正があっても耐えられる安定したポートフォリオを築けます。
- 減価償却終了後も家賃収入のみで安定化できる
- 家賃の下落がなくローン完済後に家賃収入がほぼ純利益化
- 長期保有で資産価値が積み上がり、売却益も見込める
これが「節税頼み」ではなく「資産形成」そのもので得られる成功です。
まとめ
- 損益通算とは赤字を他の所得と相殺出来る制度
- 損益通算は節税に繋がる
- 損益通算の対象外の所得もある
- 不動産投資の節税効果はあくまでも副次的効果である
- 損益通算に頼らない安定したポートフォリオをつくる